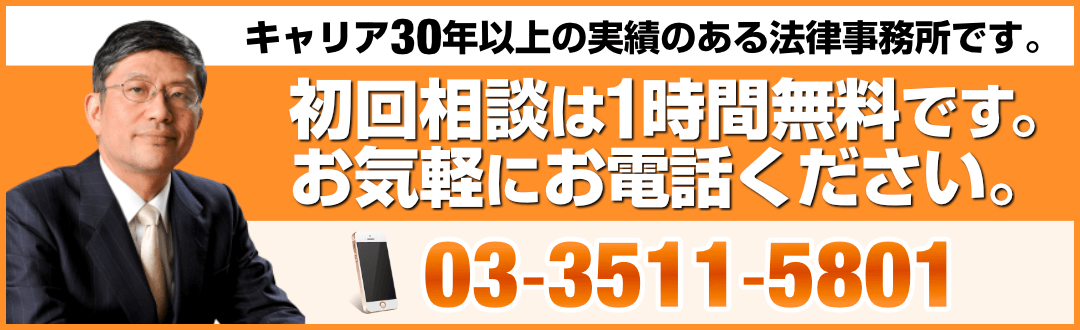上場していない企業の経営者のうち60歳以上の経営者の割合は、1990年には29.8%だったのに対して、2021年には51.8%まで大幅に上昇し、80代以上の経営者も2021年には約5%となっています。
高齢化が進んでいることに伴って、経営者が事業から退く年齢も上昇傾向にあります。1990年当時、中規模企業と小規模企業の経営者平均引退年齢がそれぞれ66.1歳、68.1歳だったのに対し、2000年にはそれぞれ67.5歳、69.8歳、2010年にはそれぞれ67.7歳、70.5歳に上昇しています。
これらを総合すると50%以上の経営者が、今後10年の間に経営者を引退する年齢に差し掛かると考えられ、まさに多くの中小企業において事業承継が大きな問題になることが予想されます(以上、日本弁護士連合会 日弁連中小企業法律支援センター編「中小企業法務のすべて【第2版】」242頁以下)。
事業承継には、①子供等の親族に承継する親族内承継、②社員等に承継する企業内承継、③第三者にM&Aなどで承継する第三者承継などがあります。
③の第三者への承継の場合は全部の株式の譲渡が前提となりますし、①②の場合であっても、承継者からすれば、できるだけ多くの株式を取得すること及び他の株主が友好的であることが望まれます。
上場していない企業の大部分は、その株式を譲渡制限付株式としています。しかし、その株式が少しずつ多数の株主(以下、「少数株主」といいます。)が、ままあります。
これは、旧商法時代の会社法において、株式会社の設立に7人以上の発起人が必要とされたことや、相続税の節税対策として支配株主以外の株主にも取得させたことなどが原因と考えられます。
しかし、少数株主であっても、株主としての権利は持っています。例えば、1株しかもっていない株主であっても、その株主に総会招集通知を送付せずに株主総会を開催し決議を行えば、株主総会決議の取消しの訴え等を提起することは可能です。
そこで、事業承継などの準備として、少数株主の株式を支配株主又は会社が取得していることが必要です。けれども、これには、長期間がかかることが多く、早めにとりかかることが必要です。
このための方法としては、合意による株式の取得を始めとして、相続等における株式売渡制度(会社法174条~177条)、所得条項付株式(会社法2条19号)、取得請求権付株式(会社法2条18号)、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法179条~179条の10まで)など、様々な制度があります。
ただし、それぞれの制度が、メリット、デメリットがあり、会社の形態によっても、メリット、デメリットが異なります。
会社が健全に相続(事業承継)されるためには、事前に会社の株式などが正常な形となっていることが必要です。このような場合、会社法及び事業承継(相続)に、強い弁護士にご相談下さい。