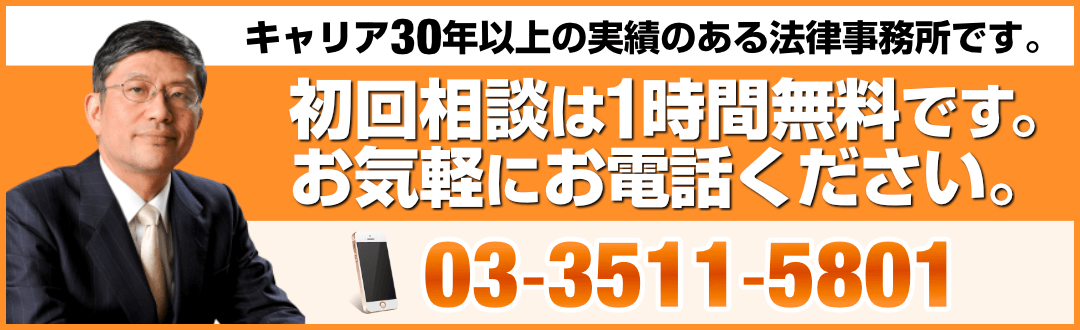判例紹介:会社の同意があっても、相続した非公開会社の準共有株式の単独での権利行使を否定した判例(最高裁平成27年2月19日 民集69巻)
事案
A非公開会社(譲渡制限付株式発行会社)の全株式の2/3の株式を保有する株主Bが死亡し、その保有株式が相続によりBの子であるXとYの1/2ずつの準共有となった。相続人の1人であるYは、Xと協議することなく、A社の株主総会において単独で、①取締役の選任、②代表取締役の選任、③本店の住所地の変更及び④それに基づく定款変更について、賛成の議決権を行使し、決議が行われた。A会社は、後記会社法106条但書に基づきYの議決権行使に同意した。
Xは、上記の決議方法については、法令違反があると主張して、本件各決議の取消を求めた。
内容
地裁は、本件準共有株式についての上記Yの議決権行使については、会社法106条但書により、A社が同意をしていることから、各決議は有効として、Xの請求を棄却しました。これに対し、原審(東京高裁)は、本件議決権行使は、不適法であり、決議の方法に法令違反があるとして、本件各決議を取り消しました。
最高裁は、「会社法106条本文は,「株式が2以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない。」と規定しているところ,これは,共有に属する株式の権利の行使の方法について,民法の共有に関する規定に対する「特別の定め」(同法264条ただし書)を設けたものと解される。その上で,会社法106条ただし書は,「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」と規定しているのであって,これは,その文言に照らすと,株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。
そうすると,共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。
そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」
と判断し、準共有持分の過半数を有さないYの議決権行使を法令違反として、本件各議決を取り消すこととし、上告を棄却した。
説明
本判決の意義
合意により、株式が共有されることもありますが、多くの場合、株式の共有が行われるのは株主が亡くなった場合です。
株主が亡くなり、相続が開始すると、その株式は相続人間で、相続分に応じて、準共有され(民法264条)、遺産分割がされるまで、その状態が継続することになります。
※「準共有」とは、数人で所有権以外の財産権(この場合は「株式」です。)を有することです。
プライム・スタンダード・グロースなどの市場の会社の株式であれば、通常の遺産同様、売却して換価して分割(換価分割)、誰か1人が取得して、他の相続人に相続分の金員を支払う(代償分割)などで分割されます。
しかし、非公開会社の場合は、株式が当該会社の経営権に結びついていることが多く、会社の相続ともいうべき事業承継も絡んで、その株式の権利行使が問題となります。本件判決もそのような場合と考えられます。
会社法106条は、本文で
「株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」
と定め、ただし書で、
「ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」
と定めています。
本件事案では、相続により株式を準共有されたXY間で、事前には協議なく、また、A社に権利行使をどちらがするか等を届け出ていないにも関わらず、YがA社の株主総会で議決権行使を行い、各決議が行われたことから、その決議が取り消されるかどうかが問題となりました。
これに対し、最高裁は、民法と会社法の条文解釈により、前記のような結論を出しました。
この会社法106条ただし書は、平成17年に会社法が商法から分離され、新たに定められ時に創設された規定で、趣旨が不明とされていました。
このように相続などにより株式が共有されている場合の権利行使の仕方について、不明であった点を①明確にした点に本件判決の意義があります。
なお、本件に適用される民法の共有の規定は、後記のように改正され、令和5年4月1日に施行(しこう:法律の効果が生じること)されました。
本判決は、この施行の前に出されたものですから、旧法によるものですが、新法になっても、改正は本件の理由・結論に影響を及ぼすものではありません。
一般法と特別法
さて、本件判決において、最高裁判所は、条文解釈の前提として、条文操作を行っており、それを理解していただくために、まず、一般法と特別法の概念について、説明いたします。
一般法とは特定の事項や人を限定せず一般的に適用される法律であり、特別法とは一般法と比較して、特定の人・事項・物に対して適用される法律です。特別法が適用される領域では、特別法は一般法に優先して適用されます。
とはいえ、一般法と特別法は、相対的な概念です。本件判決の場合は、民法が一般法で、会社法が特別法です。しかし、上場会社の場合、金融商品取引法が適用される場面がありますが、この場合は、会社法が一般法、金融商品取引法が特別法になります。
本件判決の事例で言えば、株式の共有について
【一般法】①民法252条(共有物の管理-過半数による決定)
↓
同法264条(準共有)「法令に特別の定め」
↓
【特別法】②会社法160条 本文 原則 会社に対する権利行使者の通知
↓
ただし書 例外 会社による権利行使の同意
というように条文が操作をすることになります。
本件判決の趣旨
前記の条文の操作を前提として、本件事例を考えると、本件の場合、①及び②がないことになりますが、例外であるただし書による会社による権利行使の同意はあります。
そこで、会社による権利行使の同意により、②だけが不要となるのか、それとも、①の共有物の管理についての過半数による決定も不要となるのかが問題となることになります。
そして、最高裁の判決は、前記のとおり、
Ⅰ 「会社法106条ただし書は,「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」と規定しているのであって,これは,その文言に照らすと,株式会社が当該同意をした場合には,共有に属する株式についての権利の行使の方法に関する特別の定めである同条本文の規定の適用が排除されることを定めたものと解される。」
Ⅱ 「そうすると,共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではないと解するのが相当である。」
としています。
「Ⅰ」の部分では、ただし書というのは、「文言」からすると、本来、本文の例外であり、前記で言えば②の本文の適用の排除だけを定めたもの、つまり、①の共有物管理において持ち分の過半数で決めることが必要ということは排除していないと述べています。
そして、①の適用が排除された本件事案においては、Yの議決権の行使は不適法としているのです(Yは1/2の相続分しか持っていません。)。
むろん、最高裁は文言だけで決めているのではなく、明記されていませんが、権利行使者として指定・告知されていない者による権利行使が、会社の同意があれば常に適法になるとするのは、会社側の恣意的選択を許すこととなる点問題があることも考慮した上での結論と考えられます。
本件のような事案は、非公開会社の支配株主(多くの場合、経営者でもある。)が亡くなり、会社の経営権に争いが生じた場合にまま生じる事案です。
このような場合は、会社法及び相続に強い弁護士に相談することを、おすすめします。
民法
【令和3年改正前】
第252条 (共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
第253条 (共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 省略
第264条 (準共有)
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
【令和3年改正 令和5年4月1日施行】
第252条 (共有物の管理)
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2~4 省略
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
第264条 (準共有)
この節(第262条の2及び第262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。