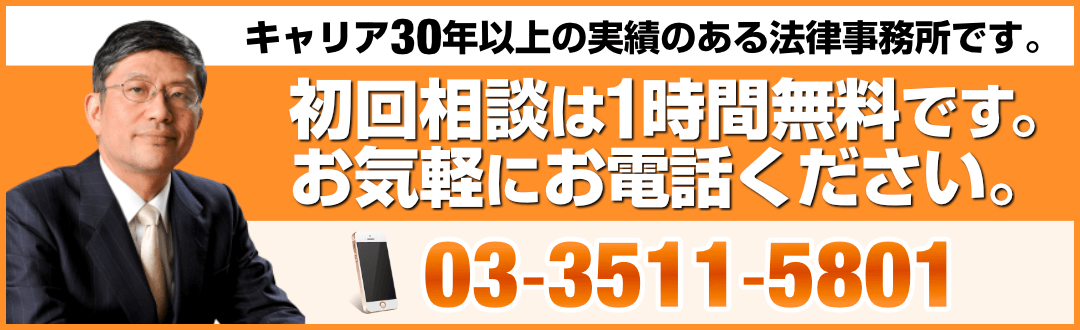少数株主対策-合意による購入の事例
甲社の発行済み株式総数は500株です。甲社の代表取締役として経営しているAは甲社の株式を300株、Bは100株、C及びDは30株ずつ、E及びFは20株ずつ所有していた。
このような場合に、将来の事業承継、上場などのために、経営株主の議決権割合を高める目的などのために、実務上使用される方法としては、まず、少数株主の株式を同意により購入することが考えられます。
A社長自身が購入する場合
Aが自分の資金で少数株主(例えば「C」)から、甲社の株式を購入する場合は、譲渡制限株式については甲社の取締役会の承認を得ることが必要ですが、Aが代表取締役ですので、その手続きは容易です。
A対Cの交渉で値段等も決められますし、買い取り時期を、買い取り資金との関係で調整した時期にもできますし、Aが予約完結権をもつなどを契約内容とすることもできます。
甲社による自己株式の取得
しかし、購入資金の関係などで、Aではなく甲社がCから甲の株式(自己株式)30株を取得しようとする場合は、会社法の定める手続きと規制をクリアーする必要があります。
株式会社が自己の発行する株式を有償で取得することを自己株式の取得といいます。自己株式の取得は、出資の払戻と同じ結果となるので会社の債権者を害するおそれがあることや、特定の株主からの買い取りは株主平等原則に反するなどの政策的理由から、かつて(平成13年6月商法改正前)は原則として禁止されていました。
しかし他方で、事業拡大の投資先が見当たらない中で資金が余剰になっている場合に、自己株式の取得によりROE(自己資本利益率)などの資本効率指標の改善を狙うニーズなどがあったことから、平成13年6月の商法の改正は、一定の手続及び制約を定めることを前提に、自己株式の取得を認め、会社法もこれを引きついています。
株式会社はその保有する自己株式について、議決権を持たない(会社法308条2項)ですし、剰余金の配当も受け取ることができません(会社法453条)。そこで、上記の事例によると、甲社がCの自己株式30株を取得すると、Aの甲社における議決権割合が、300/500から、300/470になり、Aの議決権の割合が増えることになりますし、Aに対する配当も増額されることになります。
甲社が自己株式を取得する方法としては、Ⅰ すべての株主に申込の機会を与えて行う取得と、Ⅱ 特定の株主からの取得があります。
【原則】すべての株主に申込の機会を与えて行う取得の方法
この方法は、すべての株主に対して申し込みの機会を与えて、株主から株式を取得する方法です。株主すべてに平等に申し込みの機会を与えることから、「ミニ公開買付け」と呼ばれることもあります。
合意による自己株式の取得については、この方法が原則です。
この手続き及び後記の特定の株主との合意の手続などにより自己株式を取得する場合は、自己株式の取得は、出資の払戻と同じ結果(会社から金員が支出される)となることから、剰余金の配当(決算によって確定した繰越利益剰余金等を分配すること)などの場合と同様、分配可能額(会社法461条2項)を超える場合には、金銭等を交付できず、自己株式の取得ができません。この財源規制については、また別の記事で、説明します。
この取得方法は、
1 株主総会の普通決議、
2 会社による株式の取得価格等の決定、
3 株主に対する通知、
4 買い取りを希望する少数株主からの株式譲渡の申込み、
などの手続を経る必要があります(会社法156~159条)。以下においては、この1~4について説明します。
1 株主総会の普通決議(会社法156条)
株主総会において、普通決議を行うためには議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要です。ただし、定款の定めによって、定足数を引き下げたり、排除したりすることも可能です(会社法309条2項)。
この場合、決議の内容は、
① 取得する株式数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
② 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く、以下この款において同じ。)の内容及びその総額)
③ 株式を取得する事ができる期間(1年を超えることはできない)
となります、これは「あらかじめ」の授権決議であり、実際に取得する決定は、次の手続に委ねられます。
2 会社による株式の取得価格等の決定(会社法157条)
① 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
② 株式1株の取得と引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
③ 数式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
④ 株式の譲渡の申込みの期日
なお、取得の条件は、均等でなければなりません(会社法157条3号)。
この「2」の決定は、取締役会設置会社の場合は、取締役会が行うことになります(会社法157条2項)。
取締役会のない会社の場合は、取締役の過半数で可能という考え方や、株主総会の決議が必要とする考え方がありますが、安全策ということであれば、株主総会の決議を行うことになります。
3 株主に対する通知(会社法158条)
2の決定について、会社はすべての株主に通知します。
4 買い取り希望の少数株主からの株式譲渡の申込み(会社法159条)
3の通知を受けた株主は、申込む株式数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにして、申込みをすることになります。申込み期日までに申込みがなされると、会社が申込み期日に承諾したものとみなされ、株式の売買契約が成立します。
ただし、株主からの申込総数が、2の取締役会の決定した①の取得する株式の数を超える場合には、各株主が申込みをした株式数の按分比例により、株式の売買契約が成立することになります。この場合1に満たない端数が生じた場合には、切り捨てることになります(会社法159条2項)。
【例外】特定の株主からの取得の方法
特定の株主からだけの買い取りは株主平等原則に反するおそれがあることなどから、特定の株主からの取得については、当該株主以外の株主も、会社に対して、自己株式の取得議案に自分も売主として加えるよう請求することができます(会社法160条2項、3項:売主追加の議案変更請求権)。
ただし、この売主追加の議案変更請求権は、
Ⅰ 市場価値のある株式で一定の要件を満たした場合(会社法161条、会社法規則30条)
Ⅱ 株式相続人等から取得する場合で一定の場合(会社法162条)
には、ないものとなります。
また、売主追加の議案変更請求権をあらかじめ定款で排除することが認められています(会社法164条1項)。ただし、株式の発行後にこの定款の変更をするためには当該株式を有する株主全員の同意を得なければなりません(会社法164条2項)。
なお、この取得方法の場合も、前記のすべての株主に申込の機会を与えて行う取得の方法の場合と同様、分配可能額(会社法461条2項)を超える場合には、金銭等を交付できず、自己株式の取得ができません。この財源規制については、前記のとおり、また別の記事で、説明します。
この取得方法は、
1 株主に対する売主追加の議案変更請求権が行使できることの通知
2 株主総会の特別決議
3 会社による株式の取得価格などの決定
4 特定の株主に対する通知
5 特定株主からの株式譲渡の申込み
などの手続を経る必要があります(会社法160条)。以下においては、この1~5について説明します。
1 株主に対する売主追加の議案変更請求権が行使できることの通知(会社法160条2項)
前期の通り、この取得方法の場合は、後記の特別決議で自己株式の買い取りが決められる予定の株主(例えば「C」)以外の株主に、法務省令(会社法施行規則28~29条)で定められている後記株主総会前の時期までに、株主総会の議案に自己を売主として追加するよう請求できる権利があります。
そこで会社は、未公開会社の場合は、原則として、株主総会の日の1週間までに(全)株主に対して、売主追加の議案変更請求権を行使できることを通知しなければなりません(会社法160条2項、会社法施行規則28条1項2号)。通常は、「2」の株主総会の招集通知として、又は、一緒に送付されます。
この通知は、未公開会社の場合は、株主総会開催前の3日前(会社法施行規則29条ただし書)までに、他の株主から、当該株主を売主として追加する請求があった場合には、つぎの「2」の総会決議内容に、その株主からも当該会社が自己株式を取得することを追加しなければなりません。
2 株主総会の特別決議
この場合の決議は、すべての株主に申込の機会を与えて行う取得の方法の場合の普通決議ではなく、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席した株主の議決権の2/3の賛成する特別決議である必要があります。
この決議の内容は、
① 取得する自己株式数
② 交付する金銭の総額
③ 株式を取得できる期間(決議の日から1年以内)
④ 特定の株主に対してのみ自己株式の申込勧誘の通知をすること。
ということになります。
なお、この決議では、取得の相手方となる株主の議決権行使は排除されます(会社法160条4項本文、例外は、ただし書:特定の株主以外の株主の全部が議決権を行使できない場合)。
また、もともと自己株式の買い取りが認められる予定だったC以外の例えば、Dが売主追加の議案変更請求権を行使してきた場合は、CとDにのみ通知を行うことを決議することになります。そして、この場合は、Dを否決しCのみを可決することはできません。
3 会社による株式の取得価格などの決定(会社法157条)
これについては、前記すべての株主に申込の機会を与えて行う取得の方法の場合の「3」とほぼ同様になりますが、「① 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)」が「① 特定の株主から取得する株式数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)」になります。
4 特定の株主に対する通知(会社法158条、160条5項)
会社は「2」で決議された特定の株主のみに通知します。
5 特定株主からの株式譲渡の申込み(会社法159条)
「4」の通知を受けた特定の株主(追加請求をした株主も含む)が、申込株式数を明らかにして、申込み期日までに申込みがなされると、会社が申込み期日に承諾したものとみなされ、株式の売買契約が成立します。
ただし、株主からの申込総数が、2の取締役会の決定した①の取得する株式の数を超える場合には、各特定株主が申込みをした株式数の按分比例により、株式の売買契約が成立することになります。この場合1に満たない端数が生じた場合には、切り捨てることになります(会社法159条2項)。
自己株式の保有
会社は、取得した自己株式を期間の制限なく保有することができます。しかし、会社は保有した自己株式の議決権を行使することはできませんし(会社法308条)、その他の共益権も持たないとされています。
また、会社はその保有する自己株式に対して剰余金の配当をすることはできません(会社法453条)。
このほか、株主割当てをすることもできません(会社法202条2項、241条2項、186条2項、278条2項)。他方、株式併合・株式分割は受けることができる(会社法182条1項、184条1項参照)とされています。
自己株式の消却と処分
会社は、消却する株式の種類と数を定めて、保有する自己株式を消却する(消滅させること)ことができます(会社法178条)。
また、会社は、保有する自己株式を処分(譲り渡すこと)ができます。この場合は、募集株式の発行(会社法199以下)と経済的実質(会社としては、自己株式を交付することにより、金員等を取得することになります。)が同じため、同じ手続き・規制の下で行う必要があります。
しかし、会社が自己株式の引受者を募集しない剰余金の配当などとして自己株式を交付する場合(会社法454条2項、)、新株予約権の行使に対して自己株式を交付する場合(会社法236条)、単位未満株式の買増しの際に自己株式を交付する場合(会社法194条)などは、募集株式の発行の手続は必要ありません。
合意による自己株式取得
したがって、甲会社が少数株主から自己株式を購入するためには、上記の手続きを行うことが必要です。非公開会社の場合は、特定の株主との合意により、自己株式の取得を行うことが多いと思います。
しかし、前記のとおり、Cからのみ(合意により)自己株式を取得しようとしても、他の少数株主が売主追加の議案変更請求権を行使した場合、その少数株主の自己株式も取得しなければなりません。
そこで、可能であれば、Cのみの自己株式の取得について他の少数株主の内諾が取れないか事前に確認することになる場合もあります。そして、他の少数株主が会社による自己株式の買い取りを希望する場合は、交渉又は、この機会にその少数株主からも買い取れないかを上記の財源規制等の観点も含め、検討することになります。
会社が健全に相続(事業承継)・上場されるためには、事前に会社の株式(自己株式)を経営株主が所有していることなどが必要です。
しかし、現在、多くの少数株主が会社の株式を取得している状態の場合、それを是正するためには会社法及び事業承継(相続)に、強い弁護士にご相談下さい。