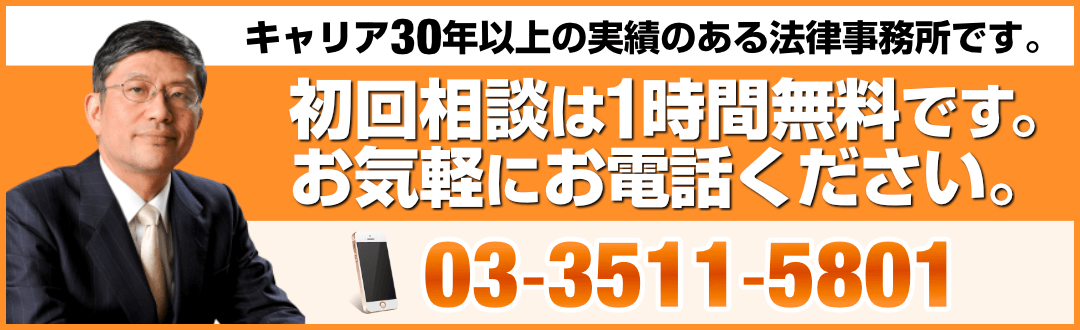調停に代わる審判とは
調停に代わる審判とは、調停において合意に至らない場合に、直ちに調停を終了させるのではなく、2週間以内に異議の申立てなければその内容どおりの効力を生じることを前提に解決案の提示をする審判です(家事事件手続法第284条)。その条文番号から、「ニー、ハチ、ヨン(284)」と呼ばれることもあります。
現在の家事事件手続法(平成25年1月1日施行)の前身である家事審判法においても、調停に代わる審判はありましたが、その対象は、離婚又は離縁の調停の場合にほぼ限られており、遺産分割調停などには適用されず、あまり活用されていませんでした。
そこで、家事事件手続法は、家事審判法から調停に代わる審判の基本的な手続きの構造を受け継ぎながら、遺産分割事件などの別表第2事件などにも対象事件等を広げるなどして、調停に代わる審判をより使いやすい形にしました。これにより、遺産分割事件も含めこの制度が大いに活用されるようになりました。
調停に代わる審判の要件(条件)
調停に代わる審判は、家庭裁判所が、調停が成立しない場合において相当と認めるとき、すなわち、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮し、事件の解決のために必要である(家事事件手続法284条1項)と判断するときは、調停に代わる審判を行うことができます。
当事者双方のために衡平に行わなければなりませんから、双方当事者が調停手続きで求めていない事項や、当事者が想定できない内容の調停に代わる審判を行うことはできません。
審判の告知
調停に代わる審判は、審判ですので、審判の告知が必要となります。
注意しなければいけないのは、調停に代わる審判の場合は、公示送達はできないということです(家事事件手続法284条2項)。
公示送達とは、送達の一種で、当事者の住所、居所その他の送達すべき場所が不明である場合など、書類を実際に送達させることが不可能な場合に、裁判所の塀等に書類を掲示するなどの一定の公示手段を執り、公示期間が経過した場合、送達の効力が発生するとする制度です。
家事事件の手続における送達については、一般的には、公示送達の方法も認められていますが、調停に代わる審判の場合は、認められないということです。
このように調停に代わる審判の場合は、公示送達が使えないのは、使えるとすると当事者の知らない間に審判の効力が生じ、異議申立権が奪われる恐れがあるからです。
調停に代わる審判の効力
調停に代わる審判は、異議申立ての期間に当事者(単独でもよい)による異議がある場合は、同審判はその効力を失います(家事事件手続法286条5項)。この場合は、家庭裁判所から当事者に調停に代わる審判が効力を失った旨を通知しなければなりません(家事事件手続法286条5項)。
遺産分割調停などの別表第2の事件に対する調停に代わる審判が、異議により効力を失い調停事件が終了した場合、調停不成立の場合と同様、調停の申立ての際に、審判の申立てがあったものとされ、審判に移行することになります(家事事件手続法286条7項)。
そして、審判手続きの中で、遺産分割を行うことになります。
当事者が調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたときは、調停に代わる審判に対して異議を申し立てることができない(家事事件手続法286条8項)とされていますが、東京家庭裁判所では、この制度はほとんど使われていないと思います。
調停に代わる審判が使われる場合
調停に代わる審判が使用される場合について、東京家庭裁判所は、家事事件手続法施行時、①合意型、②欠席型、③不一致型などに分類していたようです(矢尾和子、佐々木公「家事事件における調停に代わる審判の活用について」判タ1416号5頁など参照)。
①合意型とは
合意型とは、当事者間で事実上、合意は成立しているが、当事者が複数(多数)で、一部の当事者しか調停期日に出席できないなどの場合です。
②欠席型とは
欠席型とは、当事者の一部が、調停条項案に反対しているわけではないが、欠席を続けるなど紛争解決の意欲に欠けており、手続きに非協力的で、調停が成立できない場合です。
③不一致型とは
不一致型とは、わずかな相違で合意に至らない事案や、調停で合意を成立させることは拒否するが裁判所の判断には従うので審判が欲しいと考える当事者がいる場合です。
遺産分割調停の場合、どの類型に当たるかというより、当事者それぞれが、①から③の要素をそれぞれ複合的に持っているというパターンが多いと考えられます。
近年の民法等改正による相続登記、遺産分割等の義務化(「相続・共有に係わる民法等の法律の改正(現時点で把握すべきこと)」 https://www.kawai-sozoku.com/fudosan-sozoku/20220303-1/ 「昭和23年から現在(令和6年)までの相続に関連する法律の改正の経過:相続人、相続分等はどのように変わってきたか」 https://www.kawai-sozoku.com/kaisei/20240224-01/)などをみていただければと思います。)により、過去の遺産分割未了の遺産についての遺産分割調停の申立てが増加しています。
そして、このような事案は、数次相続(既に遺産分割未了のため、数回の相続が行われていること)となっており、多数の相続人が関与していることも多いです。さらに、高齢化社会により、相続人の高齢化(70代~90代)も進んでいます。
このため、当事者が多人数になると、遺産分割案に必ずしも反対していないが、調停に来ることもできず、電話、WWB等の対応も健康状等の理由から困難な方(合意型)や、健康状態の理由や手間から調停条項案に反対しているわけではないが紛争解決の意欲に欠けており手続きに非協力的な方(欠席型)、古い過去のことが問題となるなどからわずかな相違で合意に至らない方(不一致型)などが混在することになります。
このような場合、調停に代わる審判は、有益な手段です。
ただし、当事者の立場で、これを行うことを想定する場合は、東京家庭裁判所の運用を理解した上で、申立段階から準備を行っていく必要があります。
調停に代わる審判を見据えた準備
当事者の中で、遺産分割協議に出席できず(しない)、電話会議システムやWEB会議にも対応等をできない(しない)方がいる場合(これらが可能な場合は、調停期日に出席したことになりますし、調停を成立させることもできます。)、遺産分割協議を行うためには、調停に代わる審判を利用することが考えられます。
前記のように、調停に代わる審判の場合は、公示送達を使用することはできません。
原則的な送達方法としては、交付送達があります。交付送達には、当事者などに送達書類を郵便の特別送達(書留郵便のようなもの)で送付したり、裁判所書記官が出頭した当事者等に直接同書類を渡すなどの方法があります。
交付送達で当事者が受領しない場合、裁判所は、申立人に当該当事者の所在を調査するよう指示します。
一般的には、当該当事者の所在が不明の場合は公示送達、当該住所に当事者がいるが受け取らない場合は付郵便送達(書留郵便に付する送達)を使用することになります。
付郵便送達(書留郵便に付する送達)とは、交付送達ができない場合に、裁判所書記官が当事者の就業場所以外の送達場所に宛てて、書留郵便によって発送する方法です。
調停に代わる審判では、公示送達は条文上使用できませんが、付郵便送達は使用できることになります。しかし、裁判官によっては、付郵便送達の使用についても、慎重にされる方がいます。
このように、申立の後に、交付送達ができないことがわかると、送達等に余計な時間がかかるなどの問題が生じます。
そこで、欠席されると思われる当事者がいるなどの場合は、申立前に、当該当事者を含め、相続人全員に郵便などが届くかを確認することが望ましいですし、できれば、依頼者の遺産分割案への意向も確認したいです。
そこで、依頼者からは連絡がつかない相続人がいる場合は、弁護士の方から、手紙を出すなどして、相続人に連絡をつけたり、その遺産分割案への意向を確認することになります。
遺産分割調停で欠席者がいる場合の東京家庭裁判所の運用等
さて、遺産分割調停に欠席者がいる場合、東京家庭裁判所のいわゆる段階的進行モデルにおいては、どのように取り扱われることになるのでしょうか。
範囲合意について
民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とされています。
したがって、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始時に被相続人の財産は、原則として、遺産となります。
しかし、調停及びにおいて、遺産を分割するためには、その遺産が分割時にも存在することが必要ですし、未分割であることなどが必要です。
そこで、当該遺産分割において遺産としてどのようなものがあるかについて、合意を行うのが範囲合意です。範囲合意については、本来は相続人全員が同意することが原則です。
しかし、相続人の一部が欠席し答弁書などの書面も提出しない場合はどうしたらよいでしょうか。
この場合も、出席相続人全員が合意すれば、欠席当事者が合意しなくても、範囲合意することが可能です。
問題は、出席相続人の一部が、欠席した相続人が遺産である保管現金(タンス預金、相続開始後に預金から引き出した金員など)を保有していると主張した場合などです。
この場合は、このままでは、範囲合意ができないため、欠席当事者が、答弁書等の書面又は意向調査で保管現金を認めることにより範囲合意を行うか、主張していた出席当事者にその主張を撤回してもらい、範囲合意を行うことになります。
評価合意について
遺産の範囲の合意ができたら、次に、その遺産の評価が問題となります。預貯金や上場株式等の評価は、資料から確定できますので、あまり問題となりません。
また、出席当事者全員が換価分割また共有分割を希望しており、後記の意向調査で欠席当事者にも実質的に反対の意向がない場合(かつ、特別受益や寄与分の主張がない場合)には、評価合意は不要です。
そこで、遺産の評価が問題となるのは、代償分割などが予定されている場合の不動産や株式などの評価ということになります。
不動産や株式の評価については、正式審判の場合は、当事者全員の合意又は鑑定で確定することが必要です。
しかし、調停に代わる審判の場合は、欠席当事者は、調停に代わる審判が前提としている評価に反対する場合は、異議の申し立てをすれば、正式審判でやりなおすことができることから、出席相続人全員の合意があれば足りると解されています。
そこで、不動産や株式の評価については、出席当事者全員の合意があれば、評価合意が成立したとして扱われます。
意向調査について
調停に代わる審判の内容である条項に1人でも反対する当事者がいる場合は、同審判は行いません。したがって、まず、少なくとも出席当事者については全員合意していることが必要です。
問題は欠席当事者の意向です。予定される条項についての欠席当事者への意向調査が重要となります。
欠席当事者が答弁書等の書類が提出される場合には、その書面から意向を確認する等します。しかし、このような書面が提出されないこともままあります。申立人などに代理人として弁護士がついている場合には同弁護士にできるだけ、欠席当事者の意向を調査することが指示される場合もあります。
しかし、欠席者の意向がはっきりしない場合などには、東京家庭裁判所では、家裁調査官による意向調査を行うことが多くあります。この意向調査は調停に代わる審判の内容である条項についての調査のため、やはり、弁護士がいる場合は、その条項の作成を指示されることがあります。
その上で、家裁調査官がその条項などを郵送したり、さらに(比較的稀ですが)、電話したりして、欠席当事者の意向を調査します。
このように、遺産分割調停を行っても、出席をしない相続人がいると予想される場合などは、遺産分割に強い弁護士にご相談下さい。