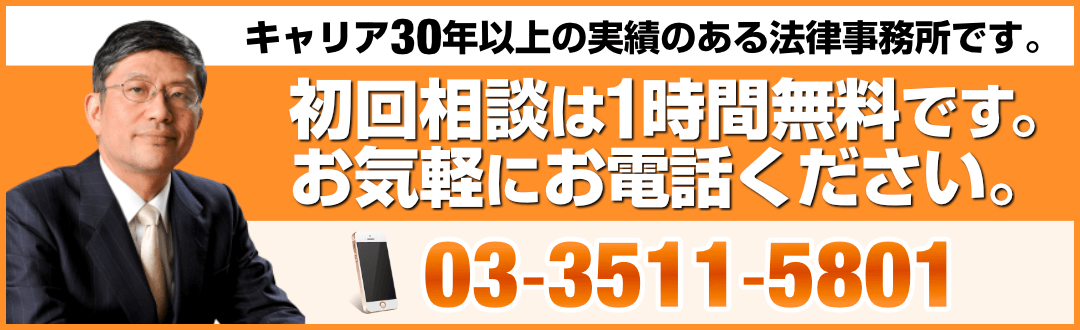現在、東京家庭裁判所本庁における遺産分割調停の新規申立て件数は、年間1000~2000件です。
ただし、この内、約4割は、申立の際、又は、調停の期日が入って、数回で取り下げられています。理由として一番多いのは、前提となる法律関係(遺産の未確定など)に争いがある場合です。この場合は、訴訟でその法律関係が確定した後、また、申し立てられることになります。
このため、常時、2000件程度の遺産分割調停事件が、遺産分割調停・審判を担当する家事5部に係属することになります。
家事5部には、5人の裁判官がいますので、この5人の裁判官が、書記官、調査官、調停委員のサポートにより、この2000件の事件を解決していきます。
上記は、現在の状況ですが、もともと、東京家庭裁判所本庁の遺産分割事件の数は、全国の家庭裁判所では、一番多く、それを相対的に少ない人員で処理をしなければなりませんでした。
大量の遺産分割事件を解決するために、生み出されたのが「段階的進行モデル」です。
また、このモデルとともに、東京家庭裁判所は、他の家庭裁判所と違い、調停内では、原則、不動産の売却を行わないという特徴があります。
さらに、他の家庭裁判所との違いは、他の家庭裁判所の遺産分割調停の調停委員は、必ずしも、弁護士でない場合がありますが、東京家庭裁判所の遺産分割の調停委員は、1人は、必ず、弁護士となっています。
このため、他の家庭裁判所では、弁護士の調停委員もその他の調停委員と同様、離婚等さまざまな調停事件を担当しますが、東京家庭裁判所の場合、弁護士の調停委員は、原則、遺産分割調停と遺留分侵害額請求調停(遺留分減殺請求調停)のみを行います。
以下においては、東京家庭裁判所の①段階的進行モデル、②調停内で不動産の売却を行わない、③遺産分割の調停委員の1人は弁護士であるという三つの特徴について、説明していきます。
まず、段階的進行モデルです。
東京家庭裁判所の遺産分割部(家事5部)は、平成11(1999)年に創部されており、遅くとも、平成24(2012)年には、段階的進行モデルが使われるようになりました(判例タイムズ1373号54頁からの「遺産分割事件の運営(上)」参照)。
この段階的進行モデルは、下記のⅠ~Vの順番で、テーマ毎に順番に交渉し、同意を行いながら調停の手続きが進められることになります。
Ⅰ 相続人の範囲(誰が相続人かを確認します。)
↓
Ⅱ 遺産の範囲(原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定します。)
↓
Ⅲ 遺産の評価(遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産・株式などの評価を定めます。)
合意できない場合→鑑定で定める。
合意できた場合
↓
Ⅳ 各相続人の取得額(Ⅱで確認し、Ⅲで評価した遺産について、法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。ただし、特別受益や寄与分が法律上認められる場合は、それを考慮して各相続人の取得額を修正します。)
↓
Ⅴ 遺産の分割方法(Ⅳの取得額に基づいて、各相続人に遺産を分割します。
分割方法には、①現物分割(その物自体を分ける方法)、②代償分割(特定の相続人が不動産などの遺産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払い調整することで分割する方法)、③換価分割(遺産を売却して金銭を分割する方法)などがあります。
この段階的進行モデルは、遺産分割調停を早く進めることを目的としたモデルではありません。話し合いが戻らず、漸進させることを目的としたモデルです。
このモデルができる前、及び、いまも多くの家庭裁判所で使われている遺産分割調停のやり方は、大雑把にいうと、申立人及び相手方の当事者が、遺産の全部あるいは1部について、それぞれの希望する遺産分割の仕方について交渉し、それが調整された時、調停が成立するというものでした。
しかし、このやり方だと、遺産分割案が合意できない場合は、また、最初に戻って、別の案で交渉しなければなりません。特に、遺産の範囲や個々の遺産の評価について合意ができていない場合、その都度、そこから、また、交渉を開始しなければなりませんでした。
このため、長い調停では、10年を超えるものもありました。
段階的進行モデルは、この方法だけで、調停を成立させることを想定している方法ではありません。段階的進行モデルのどの段階でも、当事者は相手方に対し、全体の遺産分割案を提示し交渉により合意ができれば、そこで、調停は終了します。しかし、交渉の間にも、範囲合意、評価合意等進めることにより、仮に、その案による交渉が決裂しても、合意が成立したところから、また、モデルを進めることにより、調停の進行を図ることができます。
次に、前記したように、東京家庭裁判所の特徴としては、調停内では、原則、不動産を売却しないという点があります。
他の家庭裁判所の遺産分割調停では、遺産の中に不動産があり、それらについて換価分割(売却して、その代金分割すること)する場合は、売却が完了するまで待ち、調停内でその代金の分配までを決めることが原則です。
東京家庭裁判所の遺産分割調停でも、調停が始まってから2~3回の期日間で不動産が売却できる場合や、他に特別受益や寄与分など調停で決めなければならないことが残っている場合は、売却あるいは、売買契約が締結されるまで、待ってくれます。
しかし、不動産の売却以外の遺産分割が既に終了した場合などは、売却についての任意売却の条項、さらに、定めた期間に売却できない場合の競売の条項、さらに、売却した場合の代金から売却に必要な費用を控除後の分配の仕方などを定めた条項を内容とした調停を成立させます。
この点については、埼玉県、千葉県など他の関東圏の家庭裁判所で遺産分割調停を行う弁護士が、東京家庭裁判所で初めて遺産分割調停を行われる場合に戸惑いを見せる場面が多々あります。
最後に、東京の遺産分割調停の調停委員は1人が弁護士であることについて、説明します。
段階的進行モデルは、その各段階の運用については、相続法についての理解が必要です。また、不動産を、売却を前提に調停を成立させるためには、売却後のために、どのようなことを定めなければならないかを調停委員も理解している必要があります。
このため、前記のように、東京家庭裁判所では、弁護士の調停委員は、原則、遺産分割調停と遺留分侵害額請求調停(遺留分減殺請求調停)のみを行うこととして、遺産分割調停における調停委員の1人は、弁護士がなるようにしています。
このように、東京家庭裁判所における遺産分割調停の運用は、他の家庭裁判所とは、大きく異なります。このような運用を前提として、東京家庭裁判所における遺産分割調停を迅速に自己の有利になるように行うためには、このような運用を熟知した弁護士に相談することをお勧めします。